ジャン・ルノワール監督「ゲームの規則」を観る喜び
ジャン・ルノワールという、画家オーギュスト・ルノワールの息子にして、映画史に刻まれる稀代の名監督は、私たちシネマ・ウェーブIIDAにとっても、大切な存在である。1955年に製作された同監督による「フレンチ・カンカン」は、観客がヒロインのニニとともに一喜一憂しながら次第に昂揚していくという見事な演出によって、1993年、映画の大団円・カンカン踊りのシーンを迎え、シネマ・ウェーブ会場の映画館(センゲキシネマズ)は大きな拍手に包まれた。観る者同士が一体感を覚え、映画の黄金期を彷彿とさせた。またそれは、製作から実に半世紀に近い時を超えて、映画作家とつながった貴重な体験だった。
さて、1939年に製作された「ゲームの規則」は、初公開当時、大戦前のきな臭い社会情勢にあって、ほとんどの観客から憎悪を抱かれ、野次を飛ばされ、作者ジャン・ルノワールは深く傷つき涙を流しながら映画館を出たという。その後、ルノワールの手により何度もカットされ、最終的に20分程度も短縮されたが観客の作品批判は止まず、数か月後には上映禁止となった。しかし、初公開から20年後の1959年のヴェネチア映画祭でほぼ原形に復元上映され、一世風靡されはじめたヌーヴェルバーグの若者から賞賛を浴びることとなった。日本ではさらに20年以上後の1982年、岩波ホールではじめて公開された。幸いにも私は日本初公開のその時にこの映画を観ることができた。
私はこの映画を映画史上に燦然と輝く最高傑作と評したいが、しかしこの映画を「こういう映画です」と紹介することは難しい。まず、「ゲームの規則」の「ゲーム」とは何で、「規則」とは何か、という主題に関わるナゾをきちんと説明することが難しい。この哲学的な命題を口にすることは、どこかしら口幅ったくて躊躇してしまう。そもそも「規則」というが、ルノワールがここで社会規範や道徳のような社会的なルールを描いた様にはどうしても思えない。それまでの映画のように文学的表現の装置や社会を投影する装置としてではなく、この映画で「この映画における『ゲームの規則』を描いた」のだと思う。このことは「私にとって、映画は、人生の一片ではなく、一切れのケーキだ」というアルフレッド・ヒッチコックの捉え方にも似ている。今日まで様々な人々が様々に「ゲーム」と「規則」について論じてきた中で、私が「ゲーム」の「規則」の解釈で最も共感を覚えたのは、フランソワ・トリュフォーが語った「『愛における誠実さの問題』に関する規則」という論評である。これこそが時代や国籍を超えてルノワールが真に描きたかったことなのだと思った。この映画の数年後に現れる「フィルム・ノワール」や20年程後に現れる「ヌーヴェルバーグ」の潮流を俯瞰するとき、「ゲームの規則」という映画で描いた「規則」が、その後の「映画の規則」に影響を与えたと思えてならない。
流麗なカメラワークは言うまでもなく、この映画の素晴らしい点を挙げれば枚挙に暇がないが、ここでは主要な登場人物オクターヴをジャン・ルノワール自身が演じていることにスポットを当ててみたい。当初、オクターヴ役は、ジャンの兄ピエール・ルノワールが予定されていたが、舞台の仕事の関係上出演できなくなり、代役を頼もうとしたミシェル・シモンもまたスケジュールが合わなかった。そこで自身で演じることとなる。ジャン・ルノワールは後のインタビューで「それほど必死で代役を探していたわけではないんだ。私はピエールが『自分でやればいいじゃないか、ジャン』と言うのを待ってたんだよ。その一言で十分だったさ」と語っている。ピエールからジャンへの変更に伴い、オクターヴの役柄は、愛嬌溢れる道化者へと大幅に変更された。一方ヒロインのクリスチーヌ役には、ルノワールが、若手女優の出演する舞台で役者を物色中に、桟敷席で目がとまった女性(偶然にも女優だった)ノラ・グレゴールを抜擢することとなる。ルノワールの自伝では「クリスチーヌの自分の感情に対する誠実さ」が映画の重要な要素の一つだと語っており、そのことがノラ・グレゴールが選ばれた大きな理由だったのではないかと思われる。真の主人公とも言えるオクターヴについても「自分の感情に対する誠実さ」が重要で、だからこそ監督自身で演じることにこだわったと思えるのである。初上映で観客の批判にさらされ、監督の手により幾度もカットされたのは外ならぬ監督自身が演じた箇所だったという。 しかし、ジャン・ルノワール自身が演じるオクターヴの包み込むような優しさと厳しさによって「愛における誠実さ」のルールは貫かれ、80年近い時を経た今なお、映画は瑞々しさを放ち続けている。
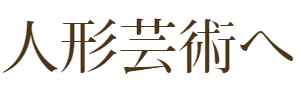



コメント