川本喜八郎人形美術館オープン1ヶ月前の2007年2月、「桃園の会」は、飯田文化会館との共催により、ゲストに映画監督の高畑勲さんを迎えて、開館前スペシャルイベントを開催。高畑監督アニメーション「パンダコパンダ雨ふりサーカスの巻」(1973)を上映した。
この作品には、大洪水の翌日、辺り一面が湖さながらの光景に変わるという美しいシーンがある。サンダルが水に浮いていたり、水中に沈んだ1階から鍋やポットを運び上げるリアルなシーンも登場する。しかし悲壮感が漂うわけでなく、登場人物たちは大洪水を受け入れ、むしろ楽しんでいる。映画はひたすら前向きに明るく未来を見据える。
フィルムは、版権を持つ会社から借りたが、高畑監督の知らないところでカットされたものだったことが、当日監督自身の指摘でわかり、上映後のトークショーが騒然としたものになってしまった。
川本先生もまた、飯田でのこれまでの映写について「上手くいった試しがない」とこの日も厳しかった。言い訳になってしまうが、ほとんどの上映会で、川本作品は35mmフィルムを用い、プロの映写技師の力を借りてきた。それでも川本先生は厳しかった。いつもは穏やかな先生でも、こと上映に関しては情け容赦なかった。考えてみれば至極もっともなことで、人形、背景、構図、色、台詞、音、音楽などひとつ一つにこだわって作り上げた作品が、観客の目に触れる最後のところ、即ち「映写」がパーフェクトでなかったら堪ったものではない、ということであった。
妥協を許さない巨匠の前で「この程度ならまあいいか」というレベルはそもそも無かった。まして今回の高畑監督のケースでは、まさかの闇編集・著作権侵害なので、監督の怒りは収まりそうもなかった。フィルムを貸し出した会社は、認識していなかったとのことだが、主催者の私たち以上に信用を失うこととなった。
さて高畑監督は、苦学生がそのまま大人になったような雰囲気が漂う人だった。高畑さんは関係者から「パクさん」と呼ばれていた。
高畑さんは2018年4月に惜しくも亡くなられ、翌月行われた「お別れの会」にスタジオジブリからご案内いただき私も参列した。その時の宮崎駿さんの弔辞。「パクさんというあだ名の謂★いわ★れはですね、(中略)東映動画に勤め始めたときも、ギリギリに駆け込むというのが毎日でございまして、買ってきたパンをタイムカードを押してから、パクパクと食べて、水道の蛇口からそのまま水を飲んでいたという、それで『パク』が『パク』になったという噂です」という言葉からも高畑監督のまるで学生のような素朴さが偲ばれる。
一昨年の朝ドラの「なつぞら」において中川大志の演じた一久は、高畑監督とアニメーター小田部羊一さんを混ぜたような設定で、様々な困難を乗り越えながらアニメーションを製作していく人物。しかしながら、現実はドラマよりはるかに険しいものだったといえる。
高畑さんの著書「『ホルス』の映像表現」に詳しい。監督第一作「太陽の王子ホルスの大冒険」(1968)では、製作期間、予算ともに、最終的に倍程度まで膨れ上がり、スタッフは処分を受けることになった。なんと高畑監督は演出助手に降格してしまう。
それでもこの作品が後に与えた影響は計り知れない。子どもたちを対象とする漫画映画であっても心の葛藤を描いたり、商業アニメの中にあっても社会的なテーマをきちんと表現した。妥協を許さぬ製作への執念や研鑽があった。処分をものともせず、飄々★ひょうひょう★と次の作品に想いを馳せていたことは、後の作品を見れば窺★うかが★い知れる。私自身、高畑さんの世間の常識みたいなことにとらわれず信念を貫く姿勢に、どれほど支えられ、気持ちが楽になれたことか。
宮崎駿さんの弔辞でもその頃のことが語られ、「パクさん、僕らは精一杯、あの時、生きたんだ。膝を折らなかったパクさんの姿勢は、僕らのものだったんだ。ありがとう、パクさん・・・」と涙で声を詰まらせながら結んだ。作品作りのためにあらゆる困難に屈しないプロの生き様だった。
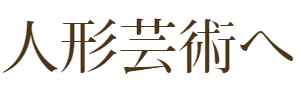



コメント