「僕は人形きり出来ない人間ですから」というのが川本喜八郎先生の口癖だった。白状すると、この何気なく発せられる口癖が私にはかなりキツかった。なぜなら、これを聞く度に「自分には何か出来ることがあるだろうか」と自問せざるを得なくなるからだ。
私にも自負心のようなものが全くないわけではないが、先生の意識にはおよそ遠く及ばない。目の前のことが上手くこなせて有頂天になったりもするが、専門性とかプロフェッショナルというより、むしろ器用貧乏という言葉がはまる。
上手いとか下手とか、好きとか嫌いとか言う前に、「どのくらいの覚悟を持って臨んでいるのか」と言われているような気がした。何か小さなことでも自分には真にこれが出来るというものを身に付けたいとも思うが、遠大な道のりを前に立ち止まってしまう。まして、「血の出るような刻苦」(故飯沢匡氏が若い頃の川本先生の研鑽を観察して表現した言葉)には到底耐えられそうもない。
当の川本先生はといえば、「人形でなければできない表現」に踏み込み、常に「人形とは何か」を追究し、妥協を許さず、試行や自問自答を繰り返して、成果を積み重ねていた。だからこそ発せられる口癖だったと思う。
心理学者で医学博士、アニメーションの研究家でもある横田正夫日本大学の名誉教授は、川本先生を「苦と悟りのアニメーション作家」と称した。2004年に開かれた飯伊仏教大学講座で、川本先生は横田氏の言葉を引用しながら語った。
「人形浄瑠璃による表現の中で一番の柱は『愁嘆』でした。愁嘆は何処から来るか、それは人生の『苦』から来る。『苦』は『執心』から来る。執心の先にあるもの、それは『悟り』です。人形というものが生まれた時から備わっている『神との関係』の中から本質が現れてくるのでしょう。『執心と解脱』これは人間に真似の出来ない人形にとっての永遠のテーマなのです」
また、遺作となってしまった「死者の書」(2005)について、先生は講座の中で次のように語った。
「最後に、郎女がその信仰によってすーッと悟りに至り、彷徨う大津皇子の魂を鎮めるのです。郎女が鎮めるのは、大津皇子の魂ばかりでなく、今日、日々癒されないまま亡くなっていく人々の魂でもあるのです」
完成した「死者の書」を拝見したとき、私は川本先生に「私には『火宅』(1979)と『死者の書』が繋がって見えます。『火宅』の菟名日処女が「死者の書」によってやっと救われた気がしました」と感想を述べた。
すると先生は、「『火宅』の菟名日処女は原作(能『求塚』)では高貴な人ではありませんでしたが、僕は菟名日処女に藤原南家郎女のテイストを入れたんです」
この奇跡的な証言に私は(静かに)歓喜した。
「火宅」の菟名日処女は二人の男性から求婚されながら選ぶことが出来ないため、周りを不幸にして地獄に堕ちる。「死者の書」の藤原南家郎女は強い力に導かれて此の世を離れ出家に及ぶ。この二人のヒロインは表裏一体、見ようによっては同じ人ともいえる。
「火宅」では人間の役者が演じたら暗く救いのない世界を、人形が持つ微かながら失われない「生命力」と、隙のない画面で華麗に結晶化させている。しかも「火宅」では、そのタイトルが物語るように、不条理な世界=火宅を「現世」そのものとしてまとめあげた。結果、この類稀な映像表現は、世界のアニメーション映画祭で称賛を浴びることとなった。
しかし、川本先生の中では「火宅」は終わっていなかった。「火宅」で表現した此の世の「苦」をそのままにしておくのではなく、「死者の書」という「悟り」の物語によって解き放とうとした。
つまり、先生は、「火宅」の製作当時から、究極の苦しみにあえぐ菟名日処女を「現世」の象徴として表現し、この処女の救い(悟り)を「死者の書」という作品に構想していた。そして26年後に見事実現したのである。 「死者の書」は川本先生自身の深い『執心』の賜物なのである。フィルムの中にこんなにも壮大なしかけを仕込み、成し遂げた他の映画監督を私は知らない。
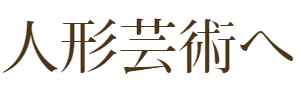



コメント